なぜ、元お笑い芸人で挫折した私が
「採用は経営そのものだ」と叫び続けるのか
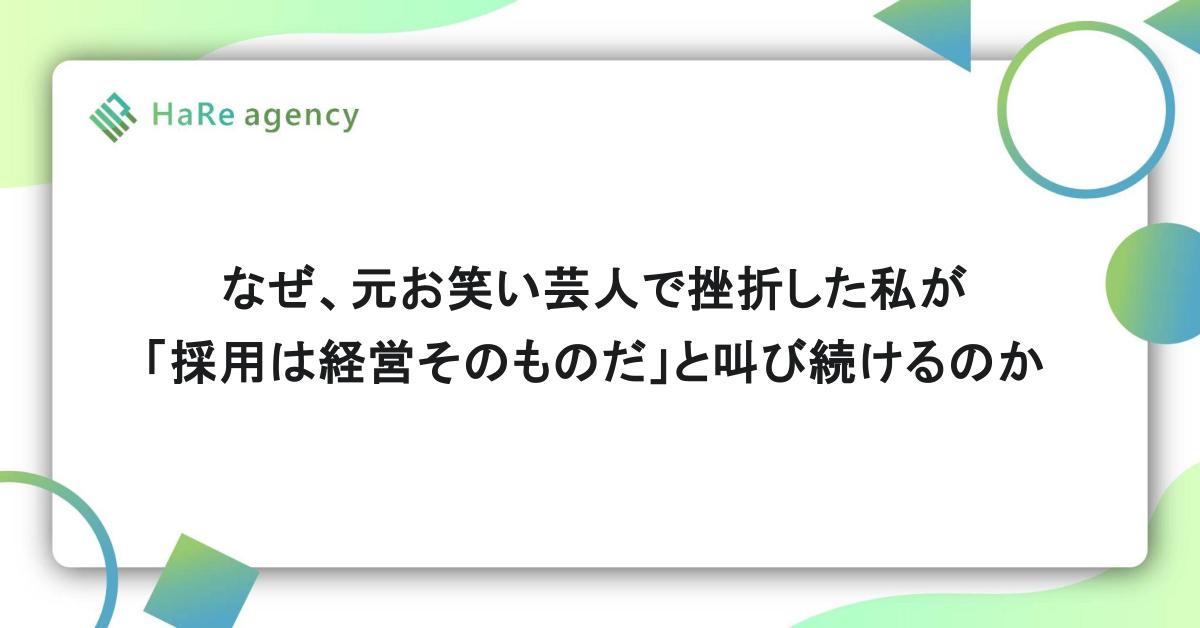
こんにちは。株式会社HaReエージェンシー代表の飯澤祥平です。
ありがたいことに、多くの方とお会いする中で、自己紹介をすると必ずと言っていいほど聞かれる質問があります。
「なぜ元お笑い芸人なのに、今は人事や採用の仕事をしているんですか?」
その答えは、私自身が回り道をし、夢に破れ、それでも見つけた「確信」の中にあります。私がなぜ「採用は、採用して終わりという“点”ではなく、その先の定着・活躍、そして事業成長にまで繋がる“経営そのもの”だ」と信じ、伝え続けているのか。
今回は、その背景にある私の原体験と想いを、少しだけ語らせてください。
Menu
すべての始まりは、教室の片隅での「心のツッコミ」だった
今でこそ経営者として人前で話すのが仕事ですが、何を隠そう、私の原点は人見知りで引っ込み思案な、自信のない少年時代にあります。太っていた見た目もあってか、人と関わるのがとにかく苦手。でも不思議と「人」への興味は人一倍強くて、いつも教室の片隅で人間観察をしながら、心の中でツッコミを入れる毎日でした。
転機は、小学校の国語の授業です。先生に突然指名されたとき、ぼーっとしていてどこを読んでいるか全くわからなかった。怒られるのが怖くて、謎の間をとった後、ヤケクソで堂々と全く違うページを読んだんです。
それがなぜか、クラスに大爆笑を生みました。
授業の後、クラスメイトが「あれ、わざとやったの?面白かったよ!」と話しかけてきてくれた。本当はただの失敗だったのに、見栄っ張りな私は「まあね」なんて得意げに振る舞って。でも、心の底では雷に打たれたような衝撃を受けていました。
「自分の行動一つで、こんなにも人の心を動かせるのか!」
その感動が、私の人生の羅針盤になりました。それからは、とにかく「人を笑わせたい」一心で、目立ちたがり屋の性質が全開に。周りから見れば8割はスベっていたかもしれませんが、たまに来る2割の笑いが、私を救ってくれたんです。
「笑い」に全てを捧げた日々。夢が、人見知りだった私を変えた
「好きなことを仕事にしたい」。その一心で、大学では臨床心理学を学びながらも、お笑いの世界に飛び込みました。
大阪のNSC(吉本の養成所)には、年間600人もの「お笑いに命をかける」と決めた猛者が全国から集まってきます。毎日が刺激と勝負の連続。ツッコミがうまそうな同期をカフェで口説き落としてコンビを組んだり、河川敷で夜通しネタ合わせをしたり。
初めて舞台に立った日、頭が真っ白になり、足がガタガタ震えた感覚は今でも忘れられません。もちろん、数え切れないほどスベり、恥をかき、悔しい思いもしました。でも、人生のすべてを捧げて「どうすれば、目の前の人を笑わせられるか?」を追求した時間は、かけがえのない経験になっています。
なにより、あれだけ人見知りだった私が、何百人ものお客様の前で堂々とネタを披露できるようになった。これは「芸人として売れる」という明確な夢と、「やるしかない」という環境が、私をとてつもなく成長させてくれた紛れもない事実です。この時、私は身をもって知ったんです。人は、夢と環境さえあれば、いくらでも成長できるのだと。
夢の終わりと、半年間の引きこもり。人生の脚本を破り捨てた日

しかし、現実は甘くありませんでした。
養成所では選抜クラスに入り、それなりに活動はできたものの、オーディションには落ち続ける。コンビ仲は険悪になり、尊敬していた先輩が夢を諦めて去っていく。気づけば、刺激的だったはずの毎日は「バイト→ネタ作り→舞台」という同じことの繰り返しになり、成長している実感が得られなくなっていました。
そして、最後のコンビが解散。
心の奥では「もう無理だ」と気づきながらも、夢を捨てる怖さ、挫折を認める怖さから逃げるように、半年間、家に引きこもりました。芸人を始めて4年、気づけば26歳。周りの友人は社会人として活躍しているのに、自分には何もないんじゃないか。そんな不安に押しつぶされそうでした。
ある日、実家で大学時代に書いた人生設計ノートを見つけました。そこには「26歳で冠番組を持ち、年収1000万、来年には女優と結婚」なんて、あまりにも大きな夢が描かれていて…。今の自分とのギャップに、泣いていたのか笑っていたのかもわかりません。ただ、気づいたらそのノートをビリビリに破り捨て、何かにすがるように、新しい人生を書き殴っていました。
ペンを握った時、一番はじめに浮かんだ言葉は「成長」でした。
芸人にはなれなかった。でも、夢に向き合ったことで得られた成長は本物だ。この経験を、今度は誰かのために使えないだろうか。
「人の成長をサポートしたい」
挫折の底で見つけた、私の新しい夢の始まりでした。
辿り着いた私の答え。経営と個人を繋ぐ「対話のデザイン」という哲学
「人の成長」を軸にキャリアを考えた時、私が選んだのは人事の世界でした。仕事の環境が人の成長に大きく関わることを、身をもって知っていたからです。
しかし、社会に出てみて驚きました。なぜ、こんなにも多くの人が「晴れやかな表情」で働けていないのだろうか、と。せっかく素晴らしい会社に入ったはずなのに、辛そうに、ただ毎日をこなしているように見える人があまりにも多かったんです。
その違和感の正体を探る中で、私は芸人時代の経験に立ち返りました。
人を笑わせ、心を動かす瞬間。それは、決して自分の一方的なパフォーマンスだけで生まれるものではありませんでした。お客様の反応を感じ取り、相方と呼吸を合わせ、その場の空気全体とコミュニケーションをとるような、濃密なやりとり。まさに双方向の「対話」が生み出す一体感の先に、爆笑という奇跡が起きていたのです。
この気づきは、組織が抱える課題にも、そのまま当てはまると考えました。
経営者が描く会社のミッション・ビジョン・バリューと、働く一人ひとりが持つ夢や誇り。この二つがすれ違ったままでは、決して最高のチームは創れません。経営者が想いを一方的に語るだけでも、社員が自分の考えを内に秘めたままでも、組織としての一体感は生まれず、大きな力にはならないのです。
採用とは、単に人手というピースを埋める作業ではない。会社のミッションと個人の夢、その交差点を見つけ出し、双方の想いを繋ぎ合わせること。会社の未来と個人の未来を重ねるための、意図的で、濃密な「対話」を創り出すこと。
それこそが、私が辿り着いた「対話のデザイン」という哲学です。
なぜ、採用は“モグラ叩き”で終わってしまうのか

もしかして、あなたの会社でも、こんなことが起きていませんか?
経営陣は立派な事業戦略を語る。でも、現場の人事は日々のオペレーションに追われ、その戦略が採用活動に全く活かされていない。結果として、「戦略はあるけど、実行が伴わない“絵に描いた餅”」状態に…。
あるいは、逆に人事は言われた通り、目の前の欠員補充を頑張る。でも、その採用が中長期的に事業をどうドライブさせるのか、という視点が欠けている。これでは、まるで場当たり的な“モグラ叩き”です。
これは、どちらが悪いという話ではありません。
この分断こそが「対話」を阻害し、採用を経営から切り離し、あなたの会社が持つ本来のポテンシャルを解放できなくしている、原因だと私は考えています。
私たちが「HR変革パートナー」として約束する、一気通貫の伴走
だからこそ私たちは、単なる採用代行屋でない、経営と個人の「対話」をデザインする「HR変革パートナー」でありたいと本気で思っています。分断された戦略と実行を「一気通貫」で繋ぎ、貴社の変革に最後まで伴走します。そのために、私たちが約束するのは、以下の3つの価値です。
【価値1】経営者の隣で事業成長を考える「HR戦略パートナー」
私たちは、採用人数の達成をゴールにしません。その先にある「入社後の定着・活躍」そして「事業成長への貢献」こそが真のゴールです。経営者の孤独に寄り添い、事業計画から逆算した「勝つための人材戦略」を共に描きます。
【価値2】本質的な魅力を掘り起こす「デザイン思考」
あなたの会社には、あなた自身も気づいていない魅力や強みが必ず眠っています。経営層から現場まで、徹底的なインタビューを通じて本質を掘り起こし、候補者の心に響く「選ばれる理由」を言語化。ミスマッチの起こらない採用の土台を創り上げます。
【価値3】戦略を描き、成果までやり抜く「アジャイルな伴走力」
戦略は、実行されて初めて価値を持ちます。私たちは机上の空論で終わらせません。描いた戦略を泥臭く実行し、高速で改善を繰り返しながら、現実的な成果が出るまで絶対に諦めません。
これら全てが、採用を経営の中心に据える「対話のデザイン」を実践するための、私たちの武器であり、覚悟の証です。
“はたらく”で、夢を叶えられるセカイへ
私がこの仕事をしている根源的な理由は、“はたらく”人と組織のミライを、もっと晴れやかにしたい、ただそれだけです。
芸人という夢に挫折した私ですが、その経験があったからこそ、夢を持つことの尊さと、人が成長する瞬間の輝きを知ることができました。
一人ひとりが自分の仕事に誇りを持ち、「晴れやかな表情」で働く。その個人の輝きが、会社の力強い成長のエンジンになる。そんな最高の好循環を、日本中に広げていきたい。それが、HaReエージェンシーの存在意義です。
採用は、経営そのもの。
それは、会社の未来を創る仲間と出会い、共に成長していくための、最も創造的で、最も重要な「対話」だからです。
私たちの想いや具体的な支援内容に少しでも興味を持っていただけましたら、ぜひ、私たちのサービスについてもう少しだけ知ってください。貴社の挑戦を、心から応援しています。
無料HR戦略相談受付中
□採用戦略が固まっておらず、 母集団形成ができていない
□難易度の高い職種に対して、戦略的な採用が実行できていない
□離職率が高く人材定着に課題がある
□様々な業務が多忙で人材課題に手が付けられない
